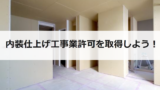2021年6月15日から、200戸以上の部屋を管理する賃貸住宅管理業者は賃貸住宅管理業登録が義務づけられるようになりました。
そこでこのページでは、賃貸住宅管理業法で求められる対応や規制・取り決めについて解説します。コンプライアンス違反にならないよう、チェックしておきましょう。
賃貸住宅管理業法ってなんだろう?
賃貸住宅管理業法とは、サブリース業者とオーナーの賃貸借契約の適正化を図るために2020年6月12日に可決成立した法律です。賃貸住宅管理業者に対して登録制度を設けることで、不動産業界の健全な発展を促すことも目的としています。
この法律の可決成立により、賃貸住宅管理業者は法の下に適正な業務を行うことが求められるのです。そのため、法律の施行時期や定められている業務などを把握しておく必要があります。
賃貸住宅管理業法の施行背景
賃貸住宅管理業法が施行された背景には、サブリースによる賃貸住宅経営の問題点が目立つようになったことが関係しています。
家賃相場が変動するリスクや賃料減額の可能性について、きちんと説明されないままサブリース契約が締結されることが少なくありませんでした。結果、サブリース業者とオーナーとの間でトラブルが相次ぐようになりました。
賃貸住宅管理業法は、サブリース契約に伴うトラブルを未然に防ぐため施行された法律です。
賃貸住宅管理業法の施行で変化すること
賃貸住宅管理業法の施行で変化するのは、主に下記の3点です。
1.業務管理者の設置が義務化
2.サブリース業者に対する賃貸住宅管理業法の規制
3.賃貸住宅管理業に係る登録制度の創設
具体的には、200戸以上の賃貸住宅を管理するすべての事業者に対して、国への登録が求められるようになりました。サブリース業者も賃貸住宅管理業を営んでいると判断されるので、200戸以上管理・保有している場合は登録を受ける必要があります。
なお、200戸未満でも登録自体はできるので、今後200戸を超えそうな場合は早めに申請しておくとよいでしょう。
サブリース業者に対する規制:不当な勧誘行為の禁止
まず、不当な勧誘行為の禁止が明文化されています。サブリース業者による勧誘の際、家賃の減額リスクや将来的な家賃相場の下落リスクなどについても正しく説明することが義務づけられました。それ以外にも、契約の可否を判断するのに必要な材料はすべて提示することが必須になりました。
事実やリスクを故意に伝えずに不当な勧誘および契約をすることは、違法行為とされたのです。同様に「家賃が減額するリスクは絶対ありません」「このサブリース契約であれば確実に利益を上げられます」など、不透明な将来を断言するような文言も禁止されました。
不動産業界は「100%」と言い切るのが難しい業界です。そのためメリットもデメリットも正しく伝えながら勧誘することが重要です。
サブリース業者に対する規制:誇大広告等の禁止
誇大広告についても、禁止事項として明記されるようになりました。例えば、前述したような「家賃が減額するリスクは絶対ありません」「このサブリース契約であれば確実に利益を上げられます」など不確定な断言も誇大広告に当たります。
なお、HP・チラシ・メールマガジン・SNSなどすべての広告媒体が対象です。セミナーの場などを利用した訴求、マンツーマンでの勧誘・相談・面談時の発言についても、不適切だとみなされた場合は誇大広告と判断されることがあるので注意しましょう。
サブリース業者に対する規制:マスターリース契約締結前の重要事項説明
マスターリース契約締結前の重要事項説明についても、賃貸住宅管理業法の施行による変化がありました。
賃貸住宅管理業法が施行される前は、マスターリース契約締結前に重要事項を説明するかどうかはサブリース業者に一任されていました。契約締結前の重要事項の説明は義務化されておらず、契約のタイミングで触れるだけでも問題ないとされていたのです。
現在はマスターリース契約前であっても、家賃・契約期間・家賃見直しの期間など重要事項を詳しく説明する義務が課せられています。口頭だけでなく重要事項説明書として交付する必要があるので、準備も欠かせません。
賃貸住宅管理業に係る登録制度とは?
200戸以上の賃貸住宅を管理するすべての事業者に対して、登録が求められるようになりました。サブリース業者も賃貸住宅管理業を営んでいると判断されるので、200戸以上管理・保有している場合は登録を受ける必要があります。
もしも無登録でこれらの業務を行ってしまった場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が課せられます。また、宅建業の欠格事由にも該当するため、管理業だけでなく宅建業の営業停止などの影響も受けます。
賃貸住宅管理業登録にはどんな要件がある?
賃貸住宅管理業登録の要件には、主に以下のようなものがあります。
- 営業所の確保
- 営業所ごとに業務管理者の選任
- 財産的基礎があるか
- 一定の欠格要件に該当していないこと
要件1~3について詳しく紹介していきます。
要件①営業所の確保
営業所は、建設業や宅建業ほど厳しい要件を課されません。ただし、法人の場合は登記上の所在と異なる場所に事務所を設置する際など、賃貸借契約書などで使用権限の証明を求められることもあります。
要件②営業所ごとに業務管理者の選任
業務管理者には、賃貸住宅管理に関する知識や経験が求められることから、国土交通省で一定の要件が定められています。
業務管理者になるためには、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
▼業務管理者の要件
1. 管理業務に関する2年以上の実務経験があり、賃貸不動産経営管理士試験に合格して資格者登録をしている
2. 管理業務に関する2年以上の実務経験を持つ宅地建物取引士で、国土交通大臣が指定する講習を修了している
2年以上の実務経験については、「賃貸住宅管理業務に関する実務講習」の修了によって代えることが可能です。
なお、2020年度までに賃貸不動産経営管理士の試験に合格して、2022年6月までに資格者登録を受けている場合、移行講習を受講していれば、上記要件の1を満たしているとみなされます。
賃貸不動産経営管理士との違い
業務管理者と賃貸不動産経営管理士は、賃貸管理業における位置づけや業務の範囲に違いがあります。
業務管理者は、賃貸住宅管理事業者に設置する役職を指すのに対して、賃貸不動産経営管理士は、業務管理者の要件とされている国家資格のことです。
賃貸不動産経営管理士は、賃貸住宅管理に関する知識・技能・倫理観を持った専門家として、所有者資産の有効活用、入居者の安全・安心の確保などの役割を担います。
業務管理者が行う業務とされていない業務についても対応して、賃貸住宅管理の適正化を図ることが求められています。
また、サブリース事業者が行う業務についても賃貸不動産経営管理士が行うことで、入居者の居住安定の確保、賃貸借事業の公正・円滑な実施につながると期待されています。
賃貸不動産経営管理士は、業務管理者が行う管理業務に加えて、以下の業務にも中立的な立場で対応することが必要です。
▼賃貸不動産経営管理士の業務
| オーナー向けの業務 | 入居者向けの業務 |
|---|---|
| ①入居者募集に関する提案経営支援・資産活用の提案入居審査の調整賃料の改定家賃滞納者への対応 ②空室管理原状回復についての協議リフォーム工事の提案特定賃貸借契約締結時の重要事項説明 | 入退去立ち会い鍵の引き渡し敷金の管理・清算原状回復費用の算定 |
賃貸不動産経営管理士は、賃貸住宅の管理だけでなく、入居者の管理やオーナーへのコンサルティングなど、幅広い業務に対応することが期待されています。
要件③財産的基礎があるか
財産及び損益の状況が良好であることを指し、具体的には下記3つのいづれかに該当することとされています。
▼財産的基礎
- 直近の事業年度における貸借対照表が債務超過の状態にないこと。
- 直近2期の事業年度の損益計算書において2期連続で当期純利益が計上されていること。
- 直近の事業年度の貸借対照表が債務超過の状態にあった場合、負債の部から、役員からの借入金を控除することにより、資産の額が負債の額を上回ること。
賃貸住宅管理業登録の流れは?
賃貸住宅管理業登録は、主に以下のような手順で進みます。
- 証明資料の収集や申請書の作成
- 国土交通省への登録申請
- 手数料の納付
- 国土交通省での審査
- 登録の完了、登録証の交付
手続きに必要な期間(日数)
国土交通省へ登録の申請書を提出してから登録証が発行されるまでに要する審査期間は90日です。
審査にかなり時間がかかるため、きちんと事業開始前から計画的に動いていく必要があります。
登録手数料
賃貸住宅管理業の登録申請をする場合は90,000円となっています。
登録に必要な書類

登録申請にはとても多くの書類を添付しなくてはなりません。申請するときは、申請書一式を作成し、行政の窓口へ持ち込む必要があります。
- 登録申請書(1~6面)
- 定款
- 履歴事項全部証明書
- 法人税の直前一年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面
- 役員が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の身分証明書
- 役員並びに相談役及び顧問の略歴を記載した書面
- 最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書
- 業務等の状況に関する書面
- 業務管理者の配置状況
- 欠格事項に該当しない旨の誓約書
こちらに記載した必要書類は一般的なケースを元に作成しています。管理している物件数など、会社の状況によって変わってきますので、事前に行政書士等の専門家に相談されるのが安全です。
行政書士に依頼するメリット
賃貸住宅管理業登録において、登録申請書の作成や添付書類の収集などはとても手間と時間がかかるものです。特に添付書類は法務局から取得しなくてはならなかったり、税務署から取得する必要があったりなど、慣れていないと時間と労力を要します。また、申請書類に不備があると、審査がストップしてしまいます。
今まで一度も申請をしたことがないと登録をするために、どれだけの時間と労力がかかるかも未知数だと思います。そのため、行政書士に依頼することで、スムーズに申請することができ、結果的にご自身で行うより早く事業をスタートすることができます。
賃貸住宅管理業登録を受けても建設業許可が必要?
管理物件のリフォーム工事が必要になった場合、税込み500万以上のリフォーム工事を自社で請け負う場合は、建設業許可が必要になります。
建設業許可を取得する最大のメリットは、受注できる工事の金額に上限がなくなることです。
建設業許可がない状態では、管理物件のリフォーム工事は最大でも500万円までの工事しか受注できないため、受注したくても行うことができない仕事があります。しかし、建設業許可を取得すれば上限額を気にすることなく、工事を受注できるようになります。
その結果、売上高を大幅に伸ばすチャンスとなり、大きく利益を増やすことができる可能性も出てきます。
なお、リフォーム工事は建設業29業種の内装仕上げ工事業に分類されることが多いため、建設業許可が取れるのか。もし今は取れないのあればどうすれば建設業許可が取れるか事前に確認しておきましょう。
賃貸住宅管理業登録のまとめ
2021年6月15日から施行されている、賃貸住宅管理業の登録手続きについて紹介しました。
宅建業免許や建設業許可ほどハードルの高い要件はありませんが、営業所ごとに業務管理者の選任が必要ですのでまだ200戸未満の部屋を管理していても、事業拡大で登録が必要になってくることも考えられますので、早めに登録を受ける要件を満たしているのか確認しておきましょう。
手続きに不安があり代行してほしい方は、行政書士など専門家への相談をおすすめします。適切なサポートを受けられ、よりスムーズに手続きを進められるでしょう。