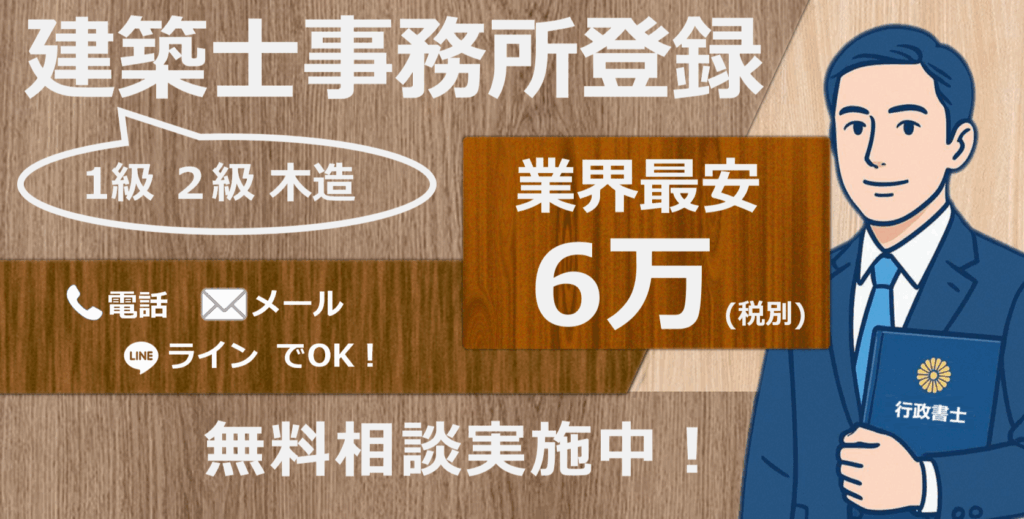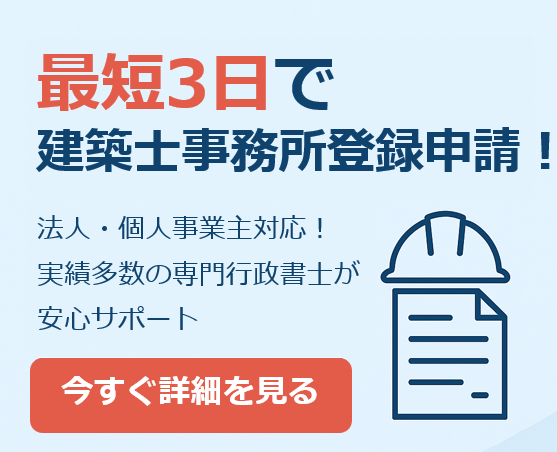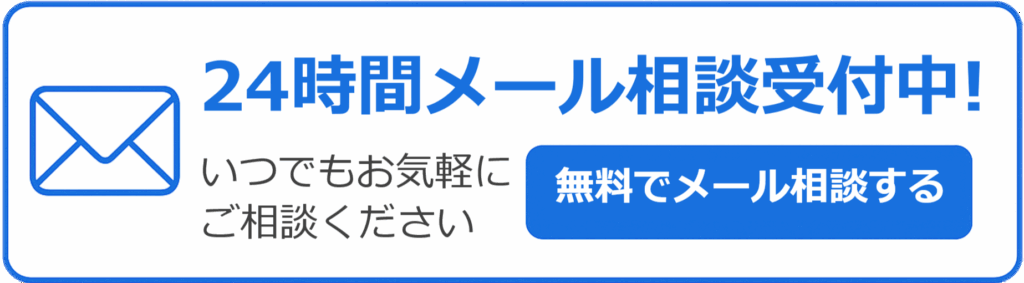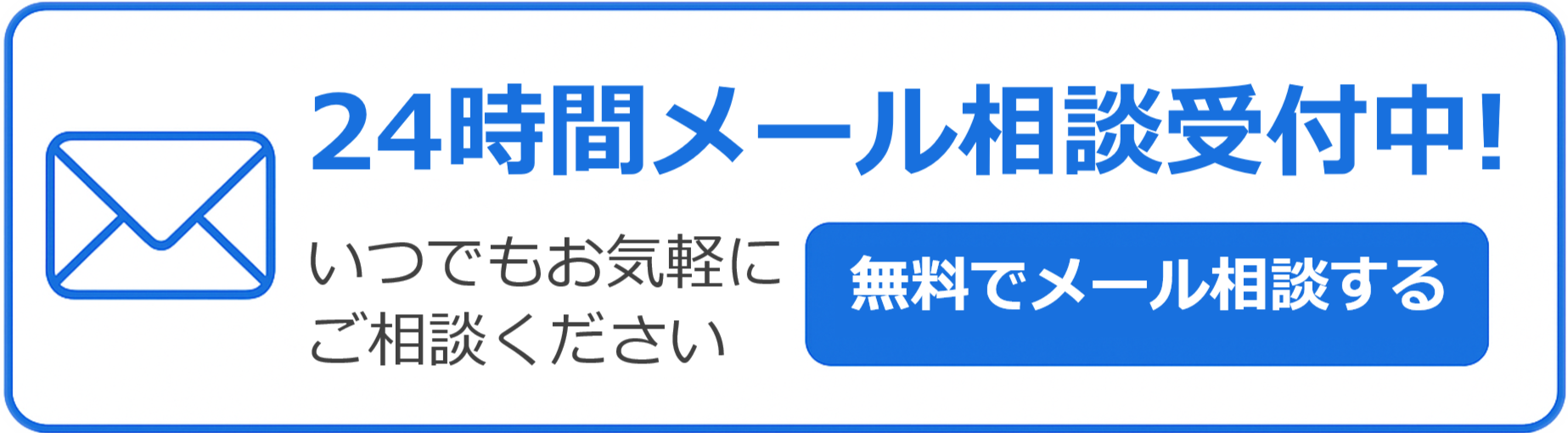「いつかは自分の設計事務所を持ちたい」
そう思い描いてきた夢が、いよいよ現実のものになろうとしています。
建築士として独立して事務所を開設する時、あるいは建設業者や宅建業者が設計業務に進出する際には、まず避けて通れないステップがあります。それが「建築士事務所の登録」です。
このページでは、事務所を立ち上げるにあたって必要な登録要件や手続きの流れをわかりやすく解説します。スムーズな開業に向けて、最初の一歩を確実に踏み出しましょう。
建築士事務所の登録が必要なのは?

建築士事務所の登録をご検討中の方から、非常によくいただくご質問がこちらです。
「どのような業務を行うときに、建築士事務所としての登録が必要になるのか?」
この疑問に対する答えは、建築士法第23条に明確に定められています。以下の業務を反復・継続的に行う場合には、あらかじめ建築士事務所としての登録が義務づけられています。
つまり、実際に設計図を作成する事務所だけでなく、たとえば建築工事の契約に関する書類作成や調整業務のみを行う場合でも、原則として登録が必要となります。
とくに大規模な建設会社や不動産会社の営業所などで、設計を直接行わないから登録は不要だと誤認されるケースが多く見られますが、実務内容によっては建築士法違反となる可能性もあるため、慎重な判断が求められます。
判断に迷うときは、必ずご相談ください!
対象業務に該当するかどうか判断が難しい場合は、無登録のまま業務を開始するのは非常にリスクが高い行為です。今行っている業務が建築士事務所登録が必要か今すぐご連絡ください!
建築士事務所登録にはどんな要件がある?
建築士事務所登録の要件には、主に以下のようなものがあります。
- 営業所の確保
- 常勤の管理建築士の配置
- 一定の欠格要件に該当していないこと
- 法人の場合は事業目的に「建築物の設計・工事監理」などが含まれること
このうち、特に注意すべき「営業所の確保」と「管理建築士の配置」について、詳しく解説します。
要件①営業所の確保
建築士事務所の営業所については、建設業や宅地建物取引業に比べると、法的な要件は緩やかです。しかし、以下の点には注意が必要です。
事務所の形態によっては、追加資料の提出を求められることもあるため、事前確認がおすすめです。
要件②常勤の管理建築士の配置
建築士事務所には、常勤かつ専任の「管理建築士」を1名以上配置しなければなりません。以下の要件をすべて満たすことが必要です。
1. 管理建築士としての資格
- 一級建築士、二級建築士、または木造建築士であること
- 「管理建築士講習」の修了証を保有していること
※定期講習の修了証では代用できません
2. 勤務形態の要件(常勤・専任)
- 管理建築士は当該事務所に常勤し、専らその業務に従事している必要があります
- 他社に勤務している建築士や、住所が事務所から極端に離れている場合は「常勤」とみなされません
- 派遣社員は管理建築士になれません
3. 他の役職・兼務との関係
- 建設業の「専任技術者」や、宅建業の「専任の宅地建物取引士」との兼任は、一定条件のもとで可能
- 同一法人・同一営業所であること - 他社の代表取締役は原則不可
- ただし「非常勤取締役」であることが明確に証明できれば、例外的に認められるケースもあります
管理建築士が欠けたとき
建築士事務所の登録後、管理建築士が退職・異動・死亡等で欠けた場合、即座に廃業届の提出が必要となります。事実上、登録は失効となり、業務継続が不可能になります。
したがって:
登録簿上で誰がどの事務所の管理建築士を担っているか、常に把握しておくことが重要です
- 人事異動・退職の前に、管理建築士の配置状況を必ず確認
- 登録簿上で誰がどの事務所の管理建築士を担っているか、常に把握しておくことが重要です
建築士事務所における「管理建築士」は、業務継続の要となる存在です。組織全体として計画的な配置・管理が求められます。
登録の流れは?
事務所登録は、主に以下のような手順で進みます。
- 証明資料の収集や申請書の作成
- 窓口(建築士事務所協会)への提出
- 手数料の納付
- 建築士事務所協会での審査
- 登録の完了、登録証の交付
手数料も事務所の種類や都道府県で異なる
また建築士事務所登録の際に必要な申請手数料の金額も、建築士事務所の種類(一級なのか二級なのか木造なのか)や都道府県によっても異なります。
通常、1万円から2万円程度となっています。
手続きに必要な期間(日数)
建築士事務所登録の申請書を提出してから登録証が発行されるまでに要する期間も、各都道府県建築士事務所協会によって異なります。
東京都の場合では、5日から10日前後で登録証が発行されることが多いですが、締め日の関係でそれ以上に日数がかかることもあります。
ウィルホープ行政書士事務所の業界最安のサポート料金
建築士事務所の登録を受けるためには、必要書類の整備や要件の確認を丁寧に行うことが重要です。中でも、管理建築士の専任は、登録における重要なポイントです。
弊社では、確実な登録取得を目指しつつ、お客様にとって無理のない費用負担となるよう、コスト面でもご安心いただけるサポート体制を整えております。
※すぐに正確な料金を確認されたい場合は、お見積もりをお送りしますので、お気軽にご連絡ください。
| 内容 | 建築士事務所登録新規申請 |
| 報酬額(税抜) | ¥60,000 |
| 登録免許税 | 1級:23,500/2級・木造:22,200円 |
建築士事務所登録は自社で取得できる?
建築士事務所登録は管理建築士の常勤性証明から退職証明書など、ちょっとしたミスや手続きの抜け漏れが大きなトラブルに繋がります。
たとえば…
これらの問題に直面した場合、後から修正や再申請が必要となり、時間とコストがかかるだけでなく、事業の開始が遅れる可能性も。自社だけで手続きを進めるのは、リスクを抱えることになります。
「これで本当に大丈夫かな?」と少しでも不安があるなら、今すぐウィルホープ行政書士事務所に相談を!手続きに精通した行政書士が、確実にサポートし、スムーズに許可を取得できるようお手伝いします。
無料相談はいつでも受付中! あなたの不安を解消し、確実な許可取得へと導きます。