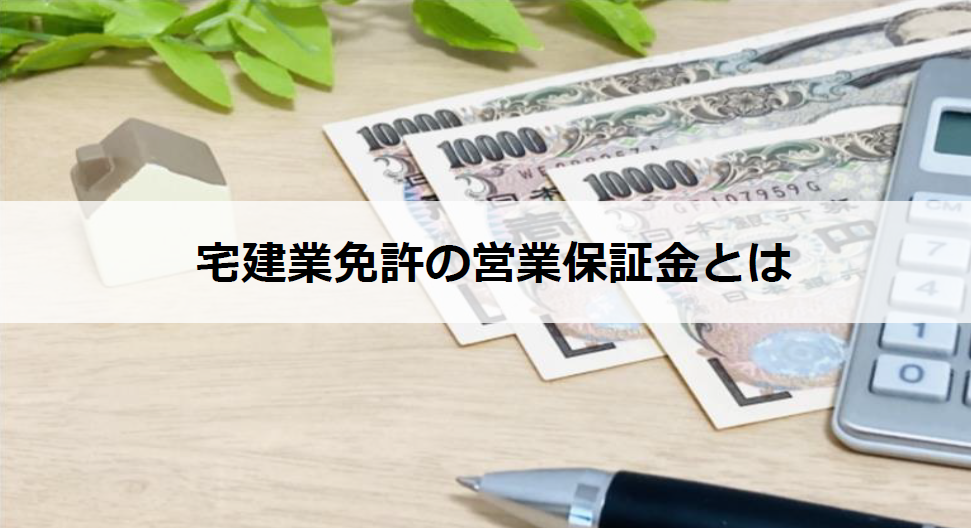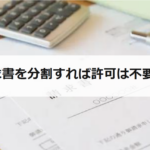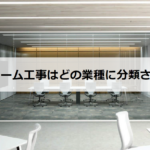宅建業を始めるにあたり、免許取得の中で「営業保証金を供託」するということが必ず必要になってきます。万が一宅建業者と取引主の方との間にトラブルが生じ損害代金を支払えない場合に、両者を守ってくれるのが営業保証金なのです。
こちらでは宅建免許の営業保証金について詳しく解説いたします
なぜ保証金を供託するの?
不動産を取り扱う宅建業では、取引される金額がかなり高額になります。その際に、もしも宅建業者と取引主の方との間でトラブルがあった場合、損害を補償しなければなりません。
しかし、宅建業者がお金を支払うことができないと、補償が行われず取引主の方が損害を被ってしまいます。取引主の方に損害を与えないよう、万が一の際に備えて事前に宅建業者から一定のお金を先に預けておくという制度があります。これを「供託」と言います。
営業保証金には二種類の供託制度があります。
- 営業保証金
- 弁済業務保証金
どちらか一方を選んで供託しなければなりません。それではそれぞれの制度について詳しくご説明していきます。
➀営業保証金について
【営業保証金の供託金額】
- 主たる事務所・・・1,000万円
- その他の事務所・・・500万円(一箇所につき)
お金・有価証券どちらでも構いません。
※有価証券の場合は評価額が異なってきますので注意しましょう。(下記参照)
- 国債証券・・額面通りの100%
- 地方債証券・・政府保証債証券:額面の90%
- その他の有価証券・・額面の80%
手続き方法は?
1.まず主たる事務所(本店)の最寄りの法務局(供託所)で申請を行います。
またいくつか支店を構えている方は、事務所がある数だけ供託金を準備しなければなりません。
2. 営業保証金の供託先は主たる事務所の最寄りの法務局、または地方今法務局・支店・出張所となります。
3.供託書の写しを都道府県知事へ届出します。
※宅建免許通知のハガキが届いてから3ヶ月以内に営業保証金の手続きを完了させないと免許取り消しにされる場合があります。ハガキが届いたら、早めの手続きを行うことをお勧めします。
主たる事務所が移転した場合はどうするの?
供託後、主たる事務所の移転により供託所が変更する場合は、新たに構える事務所(本店)の最寄りの供託所に供託金を移し替えることができます。
しかし、現金のみで供託している場合のみ行えますのでそこにも注意していきましょう。
➁弁済業務保証金について
宅建業を行う上で最低でも1,00万円の営業保証金を納める必要があり、とてもじゃないですが、この金額を一気に納めるのは難しくなってきます。
そこで、それぞれの事業者が少しずつお金を出し合い多額のお金をプールするという制度ができ、これを宅地建物取引業保証協会と言います。その中で弁済業務保証金という制度が作られ営業保証金を少しでも免除することができるのです。
それでは、次に弁済業務保証金について詳しくご説明していきます。
【弁済業務分担金の場合】
- 主たる事務所・・・60万円
- その他の事務所・・・30万円(一箇所につき)
営業保証金を支払う場合と比べるとかなりの出費を抑えられます。ほとんどの宅建業者はこのように保証協会へ加入して、費用を少しでもおさえる方が多いようです。
手続き方法は?
まず保証協会へ加入し(ハトマーク・うさぎのマーク2種類あります)保証協会による認証が必要になってきます。
宅建業者は、上記の金額を加入する日までに保証協会へ納めなければなりません。この場合現金のみになります。保証協会が1週間以内に納付された金額を供託所へ供託してくれます。
保証協会は宅建業者に対し、供託した旨の申し出を行います。
このような流れで手続きを行っていきます。
営業保証金の還付について
宅建業者と取引主の間でトラブルが生じ損害を被った者が、損害額を弁済してもらうことができます。
【還付の手続き】
・営業保証金・・供託所へ直接行います
・弁済業務保証金・・保証協会による認証が必要です
還付により供託すべき営業保証金が不足した場合には、不足金を新たに供託し、供託した旨を免許権者へ届出しなければなりません。(2週間以内に手続きしなければなりません)
営業保証金の取り戻しについて
宅建業者が、免許失効・取り消し、死亡等により宅建業を止める場合や、事務所が新たな供託所へ移転することになり営業保証金を供託した時、宅建業者が保証協会の会員になった時等、理由に応じて保証金を返還してもらうことができます。
取り戻す理由で方法が異なります
・免許失効・取り消しの場合・・請求者に対し6ヶ月以内に権利を申し出るよう公告を行い、公告した旨を届け出なければなりません。
宅建業者が保証協会の会員となり営業保証金が免除された時・・公告不要ですぐに取り戻しが行えます。
理由によっても、期間や公告した旨を届ける場所や手続きが異なってきますので注意しておきましょう。
まとめ
宅建免許を取得し、実際に営業をスタートさせるにはたくさんの複雑な手続きが必要となってきます。
これらの営業保証金の手続きを実際に行う際に、不安なことやご不明なことが少しでもございましたら行政書士など専門家への相談をおすすめします。適切なサポートを受けられ、よりスムーズに手続きを進められるでしょう。