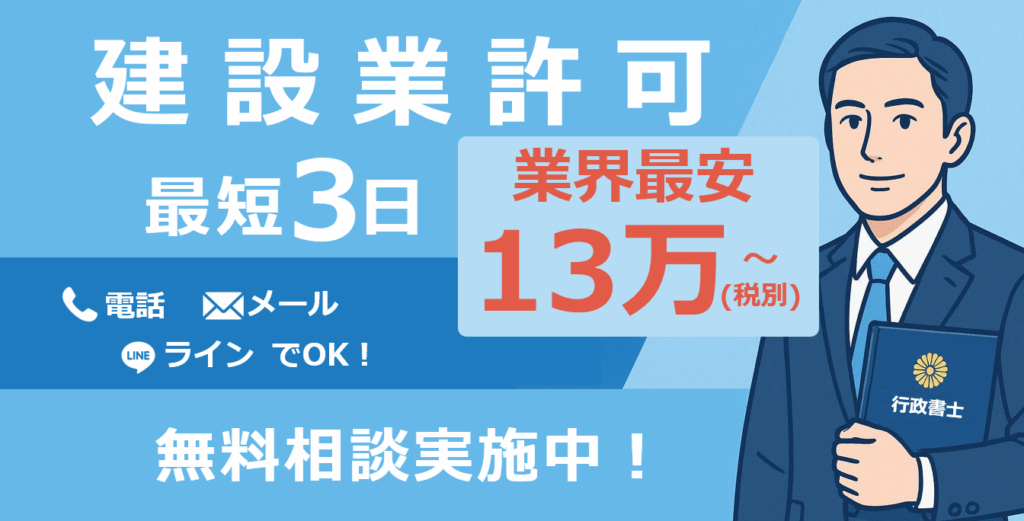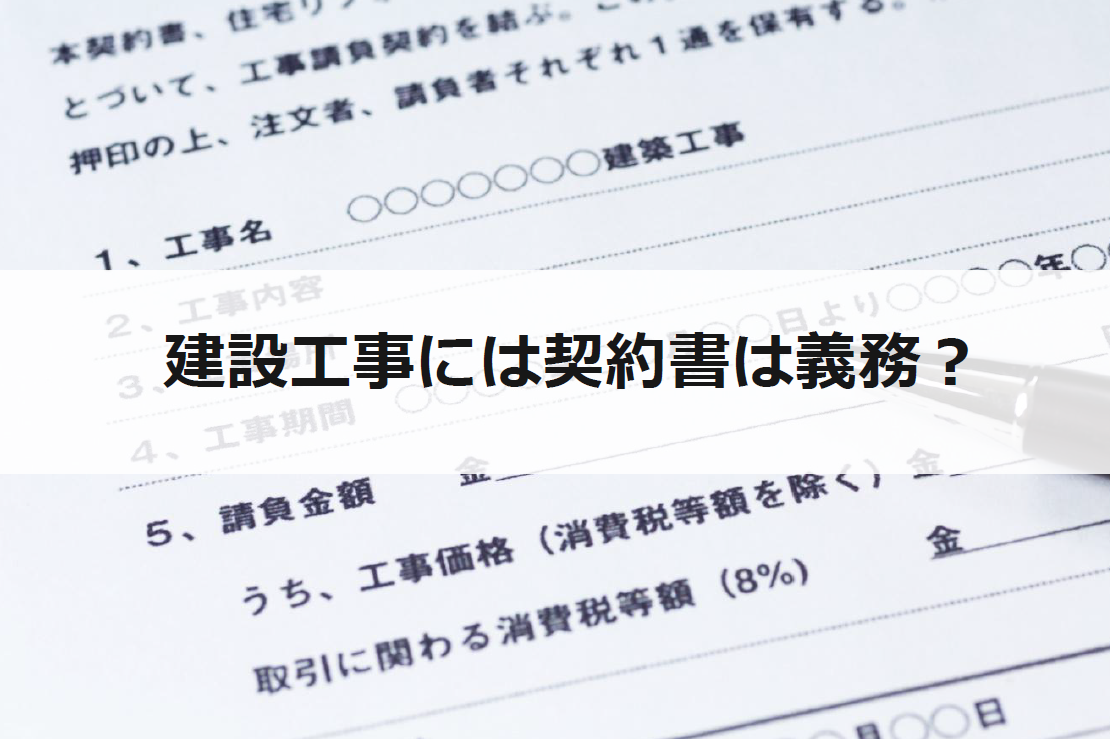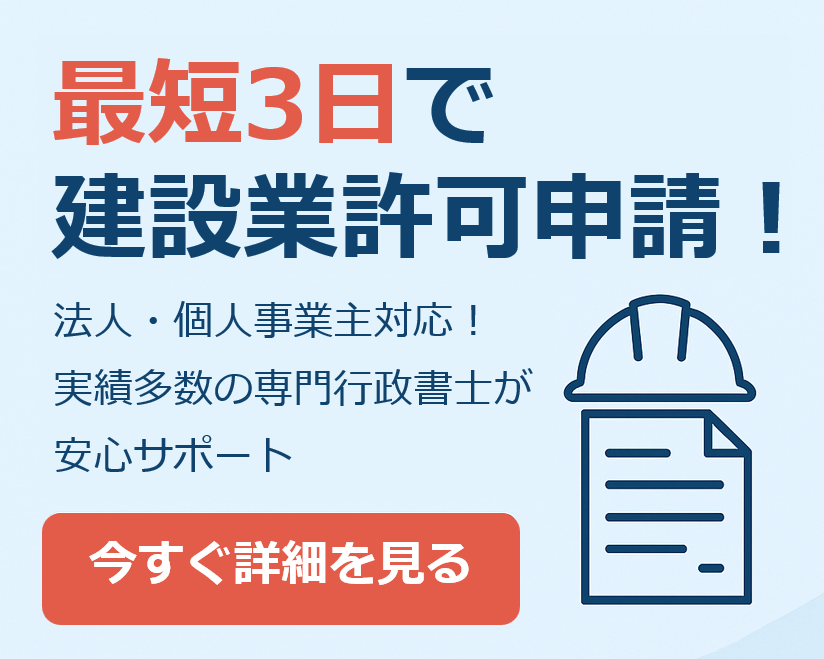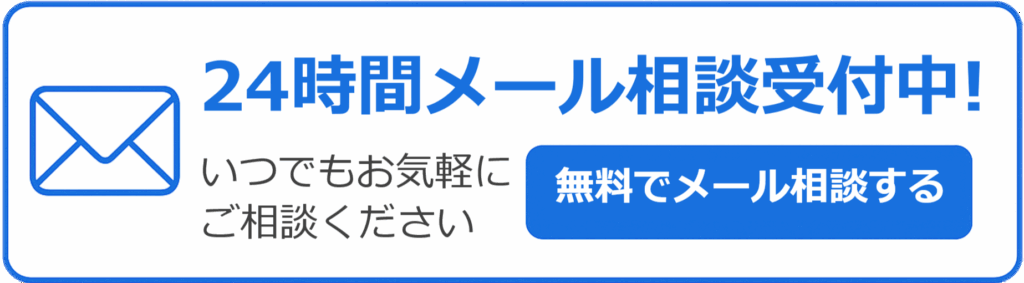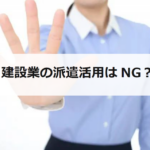建設業許可の取得を目指している方、ちょっと待ってください!
「工事請負契約書なんてなくても、今まではなんとかなってきた…」という方は要注意。実は、契約書がないだけで建設業許可の申請が通らないケースもあるのです。
このページでは、なぜ契約書が必要なのか、作成していない場合にどんなリスクがあるのかを、行政書士の視点からわかりやすく解説します。
建設業許可申請にも影響する!契約書の保管は必須
将来的に建設業許可の取得を目指すのであれば、過去の工事に関する契約書は非常に重要な資料となります。建設業許可の申請時には、過去に請け負った工事実績を証明する必要があり、その証拠資料として最も信頼性が高いのが「工事請負契約書」です。
契約書には、工事の内容・請負金額・工期・発注者の情報など、実績確認に必要な情報が網羅されています。これらがなければ、たとえ実際に工事を行っていたとしても、「実績がない」とみなされてしまうリスクがあります。
契約書を作成していなかった、あるいは紛失してしまった場合には、そもそも建設業許可の申請そのものができなくなるおそれもあります。
将来の許可取得を見据えて、工事ごとに確実に契約書を作成・交付し、正しく保管しておくことが、建設業者にとって重要な備えとなります。
工事請負契約書を交わしていない方へ
過去の実績を証明するために別の書類でも申請可能な方法をご案内いたします。お気軽に[無料相談フォーム]からご相談ください。
契約は口約束でも有効?しかし建設業では別の話

一般的な契約は、口約束でも法律的に有効です。建設工事以外の請負契約でも原則は同様です。
ただし、建設工事は民法とは異なり、「建設業法」という特別な法律で厳しく規定されています。
なぜかというと・・・
このような背景があるため、トラブルが起こりやすくなるとも言えます。契約書による明確な取り決めが不可欠なのです。
それでは、建設業において必要な契約書についてみてみましょう。
工事請負契約書とは?いつ必要?
工事請負契約書は、建設会社と依頼主の間で交わす書面契約です。建設業法第19条に基づき、以下が義務付けられています。
この契約書は、工事の規模にかかわらず必要です。たとえ建設業許可が不要な小規模工事でも省略はできません。
そして、工事請負契約を交わす際には、建設会社側が契約書以外にも約款や見積書なども準備します。これらが準備されていなければ、依頼主への説明準備が整わないため、万全の準備を整えて工事請負契約に臨みましょう。
工事請負契約書の役割とメリット
工事請負契約書は、単に契約を結ぶだけの書類ではありません。工事請負契約を交わすことで、建設に関するさまざまなトラブルやリスクを回避できる書類でもあります。
請負契約の片務性とは、契約の当事者のうち片方だけが義務を負うことであり、工事請負契約においては、建設会社が大きな義務を負うことになります。また、適正な工事請負契約書を交わすことにより、建設会社と依頼主の間での認識のズレも少なくなるでしょう。
契約書に盛り込むべき内容
契約書に盛り込むべき内容ですが、建設業法19条の規定の続きに明確に列挙されていますので、紹介します。
工事請負契約書を交わしていない方へ
過去の実績を証明するために別の書類でも申請可能な方法をご案内いたします。お気軽に[無料相談フォーム]からご相談ください。
契約書がない場合の2つの重大なデメリット
契約書を作成したなかった場合のデメリットとしては、下記2点が考えられます。
1. 建設業法違反による行政処分
2. 紛争リスクの増大
工事請負契約書がなくても申請ができる方法がある?
工事請負契約書は、トラブル防止だけでなく、建設業許可の取得にも大きく関わる重要な書類です。
契約書がないことで法令違反や申請不可といったリスクも生じます。
契約書の作成・保管は「義務」であり「将来への備え」です。不安がある場合は専門家に相談し、確実に対応していきましょう。