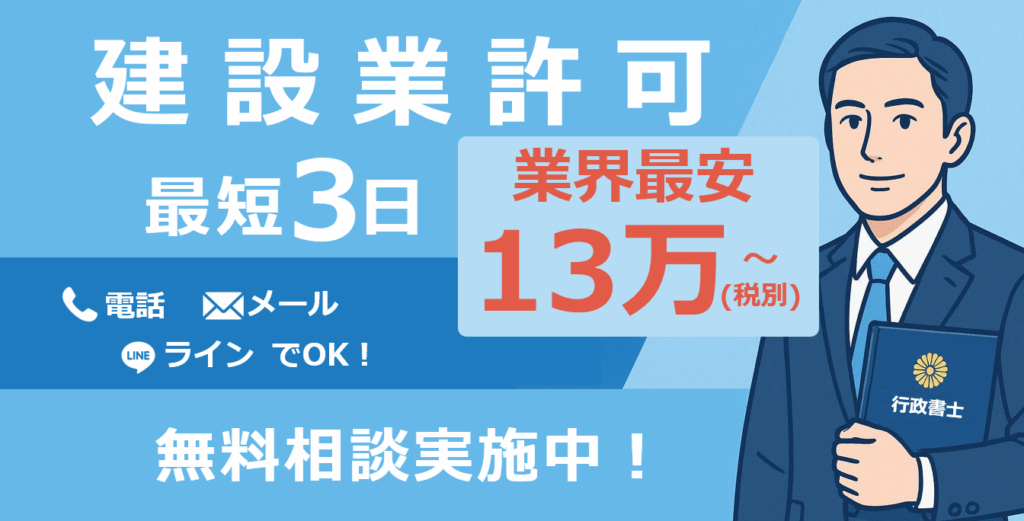価格転嫁対策や現場管理効率化などのため、「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律」について、令和6年12月13日から一部改正されました!
このページでは、建設業法がどのように改正されるかを紹介いたします。
主任技術者または監理技術者が兼務可能に!
建設業法施行令第27条に規定する重要な工事、かつ、工事1件の請負代金額が4,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)の工事は「主任技術者または監理技術者」を「専任配置」しなければいけません。
専任配置とは、その工事現場以外にかかる職務をしてはいけないことが要求されることから、専任配置が必要な工事が複数あると技術者不足となり資格者不足・人手不足問題となっていました。
ですが、今回の改正法により新設された建設業法(第26条第3項第1号)により、4,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)の工事であっても、1億円未満(建築一式工事は2億円未満)の工事の場合は「条件付き」で他の工事現場の兼務可能となります。
主任技術者または監理技術者の兼務条件とは?
改正法により、主任技術者又は監理技術者が複数の工事現場を兼務できることとなりますが、兼務するためには下記7つの条件をクリアする必要があります。
▼工事現場について
(1)1億円未満(建築一式工事は2億円未満)の工事であること
(2)工事現場間の距離が、1日で巡回可能な範囲であること(移動時間がおおむね2時間以内)
(3)各現場との間で現場の連絡ツールが整備がされていること(スマートフォン・web会議システム等で可)
▼施工体制について
(4)各建設工事の下請次数が3次まで
(5)主任技術者または監理技術者との連絡その他必要な措置を講ずるための者の配置(土木一式工事・建築一式工事の場合は、実務経験を1年以上有する者)
(6)工事現場の施工体制を確認できるICT環境の措置(CCUS等の活用)
▼運用について
(7)人員の配置を示す計画書の作成、現場据置及び保存(電磁的記録媒体による措置も可能)
令和2年の法改正時には、監理技術者補佐を専任配置すれば監理技術者の2現場の兼務ができるようになりましたが、令和6年12月の改正により兼務可能なパターンが増えました。
専任技術者も主任技術者または監理技術者との兼務が可能に!
これまで、営業所の専任技術者(建設業許可の要件の1つ)は、現場に配置される専任の主任技術者または監理技術者との兼務はできませんでしたが、4,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)の工事であっても、1億円未満(建築一式工事は2億円未満)の工事の場合は”条件付き”で専任技術者と監理技術者等として兼務可能となります。
専任技術者の兼務条件とは?
改正法により、専任技術者が下記の7つの条件をクリアしていれば、1現場までに限り主任技術者または管理技術者との兼務が可能になります。
▼工事現場について
(1)1億円未満(建築一式工事は2億円未満)の工事であること
(2)営業所と工事現場間の距離が、1日で巡回可能な範囲であること(移動時間がおおむね2時間以内)
(3)各現場との間で現場の連絡ツールが整備がされていること(スマートフォン・web会議システム等で可)
▼施工体制について
(4)各建設工事の下請次数が3次まで
(5)主任技術者または監理技術者との連絡その他必要な措置を講ずるための者の配置(土木一式工事・建築一式工事の場合は、実務経験を1年以上有する者)
(6)工事現場の施工体制を確認できるICT環境の措置(CCUS等の活用)
▼運用について
(7)人員の配置を示す計画書の作成、現場据置及び保存(電磁的記録媒体による措置も可能)
資材高騰に伴う労務費へのしわ寄せ防止
今回の建設業法等改正による2つ目の変更点は、資材高騰に伴う労務費へのしわ寄せ防止です。
具体的には、以下の改正が定められています。
- 受注者の注文者に対するリスク情報の提供義務化
- 請負代金の変更方法を契約書記載事項として明確化
- 資材高騰時の変更協議へ誠実に応じる努力義務・義務の新設
受注者の注文者に対するリスク情報の提供義務化
建設工事を請け負う建設業者は、資材不足や資材の価格高騰など、工期または請負代金に影響が出るおそれがあるときは、請負契約を締結するまでに注文者に対して、通知しなければならないものとされました。
受注者の注文者に対するリスク情報の提供により、請負契約締結前の段階で、資材の供給不足や高騰への対策に関して適切な協議を促す効果が期待されます。
請負代金の変更方法を契約書記載事項として明確化
工事内容や請負代金の額など、建設工事の請負契約に記載すべき事項が定められています。
今回の建設業法等改正により、建設工事の請負契約において、請負代金を変更する際の金額の算定方法を定めることが義務化されました。これは、資材の価格の高騰などが発生した場合に、スムーズに請負代金へ反映できるようにすることを意図したものです。
資材高騰時の変更協議へ誠実に応じる努力義務・義務の新設
資材不足や資材の価格高騰など、工期または請負代金に影響が出るおそれがあることを注文者に通知したのち、実際に影響が発生した場合には協議を申し出ることができるものとされました。
協議の申出を受けた注文者は、当該申出が根拠を欠く場合その他正当な理由がある場合を除き、誠実に協議に応ずるよう努めなければなりません。
また公共工事に関しては、工期または請負代金の額に影響を及ぼす事象の発生により、受注者が請負契約の内容の変更について協議を申し出たときは、各省各庁の長等は誠実に当該協議に応じることが義務付けられました。
【2024年12月改正】建設業法改正のまとめ
今までは技術者の現場兼務は認められていませんでしたが、建設業界は資格者不足・人手不足問題が進んでいるため、一定の条件をクリアすることで現場兼務が認められるようになりました。
現場兼務が認められることで、人員の効率的な配置が可能になるので、人員の確保が容易になりかつ人員コスト削減につながるのではないでしょうか?
しかし、きちんと条件をクリアしていることを確認しなければ知らずのうちに建設業法違反となってしまう可能性もありますので、注意が必要です。

きちんと業務を遂行するためにも、建設業法を専門にしてる行政書士にご相談いただくことをおすすめします。