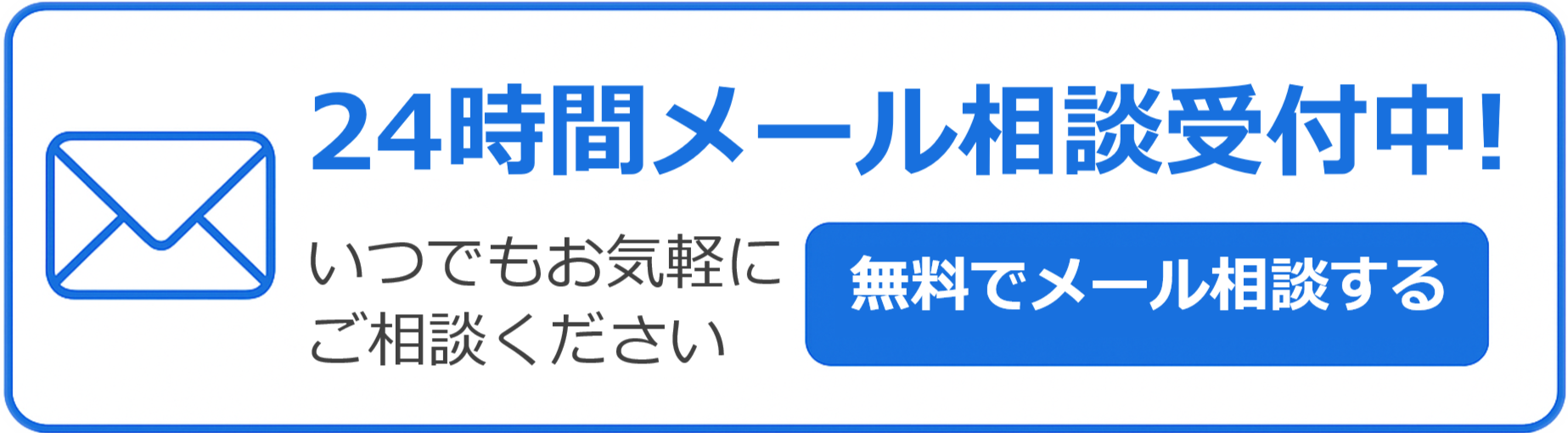このページでは、産業廃棄物中間処理施設「処分業許可」を取得したい事業者さまのために、中間処理施設の許可を取得する際の注意点について、紹介していきます!
産業廃棄物収集運搬業許可と比較して、事前計画書の提出や現地調査など、必要とされる作業がとても多いうえに、チェックも厳しいです。
重要ポイント①土地・建物の所有者からの承諾
産業廃棄物中間処理施設(処分業)の許可を取得するためには、産業廃棄物中間処理施設の土地と建物の所有者からの承諾が必須になります。
あらかじめ、中間処理施設をかりる際に、賃貸借契約書等に記載されていれば問題ないですが、使用目的が単なる倉庫や工場などは事前に所有者から承諾を受けておきましょう。
重要ポイント②周辺住民の同意
東京都の申請においては、周辺住民の同意はそこまで厳しい要件ではありません。中間処理施設に接している方、道路を挟んだ向かい側とその両隣の方が対象になります。
また、同意書をもらえなかったとしても、きちんと説明義務を果たせばこの要件はクリアとされています。
なお、埼玉県や千葉県は半径200m範囲に住んでいる方々に「個別に説明」や「説明会を実施」を行い、住民2/3以上の同意書が必要などがありますので、東京都はハードルが低いことが分かります。
重要ポイント③排水処理設備や保管場所にも細かいルールがあります
中間処理施設では、処理を行う廃棄物によって排水処理設備が必要な場合があります。→実際にはどんな廃棄物を扱う場合でも、排水処理設備が必須だと思った方がベターです。
具体的には油水分離装(グリストラップ)です。中間処理施設には車両の搬出入が多く、廃棄物には油分が含んでいる可能性があるとされいるためです。この油分がそのまま公共下水に流れてしまうと、下水道の劣化が進むため、施設から排水する前に油水分離装を経由させなければいけません。
また、屋外に保管する場合は汚水が地下に浸透してしまうのを防ぐためにコンクリートやアスファルトで舗装されている必要もあります。
中間処理施設では、下記対策が必要なので覚えておきましょう。
重要ポイント④騒音・振動対策が必須
中間処理施設には、処理機械が導入ので、騒音・振動の問題が発生します。足立区では、屋外に処理機械を設置することは認められていないので、必ず建屋内(工場内)に設置計画を立案しましょう。
しかし、建屋内(工場内)に設置したとしても、騒音が漏れてしまう可能性が高いので、例えば「防音シートで囲む」「窓を2重・3重サッシにする」「吸音材を壁に設置する」などの対策が必要です。
ちなみに、現地審査が行られる際に騒音計測がされ、規制値をオーバーすると許可は取得できませんので注意が必要です。
ちなみに、この騒音数値は複雑な数式を用いて予測をすることができます。ご自身ではかなり難易度が高いので、ウィルホープ行政書士事務所へ一度ご相談いただくことをお勧めします!
弊社代表は環境学を専攻しておりましたので、そのようなバックグラウンドからもアドバイスいたします!
中間処理施設を設置する流れ
中間処理施設を設置する場合の流れは下記ようになります。
- 東京都へ事前計画書の作成・提出
- 設置する市区へ工場設置認可申請
- 工事&設置
- 現地審査
- 産業廃棄物処分業の許可申請
それぞれ詳しく見てきましょう!
東京都へ事前計画書の作成・提出
まずは事前計画書を作成・提出しましょう。これはその名の通り、中間処理施設の場所やどのような廃棄物を保管するかなど事業活動の計画書をまとめて提出します。
必要書類としては、以下のようなものがあります。
▼事前計画書表紙
法人名や代表者氏名など会社の基本的情報のほか、積替え保管施設の所在地・用途地域・積替え保管施設の作業時間など施設に関することを記載します。
▼機械一覧
中間処理を行う機械についての処理方法(破砕・圧縮・溶融など)・一日当たりの処理能力・メーカー&型番を記載します。
▼施設の案内図
施設周辺の地図を作成し、主要な道路や駅、その他目印となるような建物をわかりやすく記載します。
▼用途地域を示す図面
準工業地域や商業地域といった用途地域を示した図面を作成し添付する必要があります。
▼施設の周辺図
施設の周辺の地図を作成します。積替え保管施設の近隣がどのような状況か分かるように作成します。
▼施設内配置図
中間処理施設の「どこに」「何を」置くのか等の施設内のレイアウトを作成し、敷地・建物の幅・長さ・奥行などの寸法を記載する必要があります。
▼施設及び施設周辺の写真
施設の周辺、施設の外観、施設内の設備の写真を撮ります。施設内の写真は、上記の写真撮影場所を示す図面で示した通りの地点から矢印の方向に向かって撮影します。
▼処理を行う産業廃棄物の一覧表
処理を行う産業廃棄物の種類、数量、保管方法などを記載します。
▼作業手順説明書
取り扱う廃棄物の種類ごとに、廃棄物の荷卸しをどのように行うか、選別をどのように行うかなど、廃棄物の取り扱いについて、細かい手順を記載することが必要です。
▼保管場所の図面及び容量計算
廃棄物の種類ごとに、保管方法、保管量、保管容器設置場所を記載します。保管場所や保管容器については、正面図、平面図、側面図および寸法の記載が必要です。保管容量についても例えば、50%勾配(1/2勾配)など複雑な計算が必要になります。
▼機械のカタログや処理能力計算書
処理機械のカタログや処理能力計算書を添付する必要があります。メーカーが発行するものが申請において記載内容の基準を満たしていない場合は、作り直しが必要になります。ウィルホープ行政書士事務所では能力計算の理解もありますので、直接メーカーと調整することもできます。
※能力を増やす・減らすなど機械の根本的能力についての助言はできません。
▼施設清掃に関する説明
施設の清掃に関して、清掃する頻度・清掃方法を記載します。
▼生活環境の保全対策に関する説明
粉じんの飛散、悪臭、騒音など生活環境へ影響を与える事項について、防止対策を記載します。例えば、粉じんの飛散については、「作業中は必ず散水を行う」とか、悪臭については、「保管場所の清掃を毎日行う」などの対策が考えられます。
▼生活環境の保全対策に関する写真及び図面
上記のオイルトラップや散水設備など、生活環境の保全対策のための設備を、写真撮影します。また、メーカーのカタログや図面がある場合には、それらも添付します。
▼使用権原を証明する書類
建物や土地を、産業廃棄物収集運搬業の積替え保管施設として使用する以上、貸主・所有者から、「積替え保管施設として使用することの承諾」を得ていることが必要となります。賃貸借契約書の使用目的の箇所に「積替え保管施設や仮置き場として使用すること」といった記載があればよいのですが、そういった記載がない場合には、「承諾書」「同意書」の提出が必要になります。
▼重機一覧表・重機の写真
施設で重機を使用する場合には、重機の一覧表・重機の写真が必要です。
▼関係法令に関する書類
建築基準法上の建築確認申請書、消防法上の許可申請書、火災予防条例上の届出書など、法令に関する申請などを行った場合には、管轄部署の受付印が入った申請書を添付することが必要です。
▼施設近隣住民等への説明内容に関する書類
積替え保管施設の設置にあたっては、近隣住民・事業者に対して、「施設で取り扱う産業廃棄物の具体的な内容」「具体的な作業内容」「環境対策」などについて説明を行い、説明を行った旨の書類を提出する必要があります。
▼説明対象者を示す図面
上記の施設近隣住民等への説明を行った説明対象者を示す図面を提出します。
▼同意書・協定書・説明経過書
施設の近隣住民、近隣事業者から取得した同意書、協定書、説明経過書を添付する必要があります。
中間処理処理施設の事前計画書の作成・提出には、上記のようなさまざまな書類や写真撮影が必要になります。なかには、施設所有者の承諾書が必要であったり、周辺住民の同意書が必要であったりと、とてもハードルが高いです。
設置する市区へ工場設置認可申請
東京都へ事前計画書の提出と同時期に、中間処理施設を設置する市区へ工場設置認可申請が必要になります。
東京都では主に廃棄物処理法についての審査を行い、市区では環境負荷(生活影響など)を細かく確認されます。
主に、騒音・振動・粉塵・水質を細かくみられるので注意が必要です。
必要書類としては、以下のようなものがあります。
騒音がかなり注目されます。用途地域や時間によって規制値が変わりますので、きちんと理解したうえで、規制値未満になるような対策をしなければいけません。
ちょっとの計算ミスでも審査が1カ月~3か月止まってしまうこともあります。
現地審査
事前計画書の作成・提出が終わったら、次は、現地調査があります。
事前計画書や工場認可設置申請では、施設内部の写真撮影や保管場所の図面や保管容量を記載した書類を提出しました。それらの書類をもとに、「廃棄物の取り扱い方法・容量・保管場所」など実際に現地を確認し、法令違反や書面上の不備がないかを東京都の職員が現地に調査に来ます。
もし、大きな不備があった場合は、何度も現地審査をしなければなりません。きちんと事前計画書通りに施設が設置されているか確認しましょう。
ちなみに、東京都と市区とで2度あります。審査ポイントも違いがありますので、東京都ではOKでも、市区がNGであれば、許可は取れず、提出書類を何度も修正する必要が出てきます。
例えば、市区の騒音計測がNGだったため、配置を変えたら、東京都の事前計画書の変更も必要なので、一度OKだったにも関わらず再度東京都の現地審査が発生します。
ウィルホープ行政書士事務所に依頼するメリット
中間処理施設の許可申請では、必要書類が多岐にわたるだけでなく、関連法令も複数にまたがるため、申請先が一つでは済まないケースがほとんどです。
そのため、単に「産業廃棄物処分業」の許可を取るだけでは不十分で、他法令での届出・許可も必要になる場合があります。
初めて申請する方は、
- それぞれの関連法令ごとに、申請先・申請方法を調べる
- 添付書類・図面・手数料などを個別に確認
- 申請前に行政へ事前相談が必須のケースもあり
- 騒音振動の予測値算出
- 申請種類によっては事前に手続き・事後の手続きなど提出のタイミング管理が非常に重要
慣れない手続きでは、書類の不備や順番の誤りで申請が進まないことも多く、事業計画立案から許可まで2年以上かかるケースもあります。
ウィルホープ行政書士事務所では、
積替え保管施設の申請に関する専門的知識と豊富な実務経験をもとに、
- 書類作成の正確性
- 各行政機関とのやり取り
- 申請スケジュール管理
をトータルでサポートします。これにより、ご自身で申請するよりも早く・確実に許可取得を実現できます。
ウィルホープ行政書士事務所のサポート料
当事務所では、確実な届出完了を目指しつつ、無理のない費用負担でサポートできるよう体制を整えております。
ご検討中の企業様は、まずはお気軽にご相談ください。
| 内容 | 中間処理施設新設手続き |
| 報酬額(税抜) | ¥600,000~¥1,000,000 |
| 登録免許税 | 約12万円 ご自身でお手続きしても発生する費用です。 |